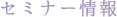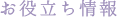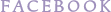【誌上テーマ別サロン】第49回
<基礎講座>
八百屋の経営はむずかしい
―「中小企業経営学入門」(49)―
1 元日航会長の言葉は本当か
・日航の再建にかつてかかわったトップ・マネジメントがどんな文脈で語ったかは正式にはわからないが、日航のこれまでの経営陣は「八百屋の経営もできない」といったという。八百屋の経営はそんなにむずかしくないのに、日航の経営陣には経営能力がないので、それもできないというようにうけとめられた。この言葉はどのようにうけとめればよいのであろうか。
・確かに、官僚的な大規模企業である日航の経営陣がスモール・ビジネスである八百屋の経営には不むきであるように思われる。もっとも、八百屋の店舗は商品を消費者に見えるように陳列し、お店の人間は消費者に声がけをして販売しているので、なんとなくその経営がわかってしまうような気になってしまう。
・しかし、新鮮度と値段、さらにブランドに敏感な消費者にむかいつつ、商品の調達と保管、価格設定に意を払わなければならない八百屋の経営は表面的に見えるものとちがって、むずかしいものと考える。時間帯や天候の具合いで在庫や価格設定の調節を考えなければならない。また、扱うのが生ものなので、過剰な仕入れもできず、破棄を少なくするような調達の管理が必要となる。
・さらに、現在の八百屋は商品の販売だけでなく、それを通じた食生活の提案を消費者に行えることが大切である。おそらく近隣の同業者への強みを獲得できるためには、その辺の配慮も求められているであろう。
2 基本の習得が不可欠
・このようにみてくると、八百屋の経営は細心さが必要であり、むずかしいといえる。日航の元会長がやさしいと考えていたのであれば、それはちがうのかもしれない。もっとも、八百屋の経営にとって必要な基本を整理して、それを習得して経営を行うならば、それほどむずかしいものでなくなるであろう。その意味で本当に必要な基本を考え、それを習得することが大切になる。
・しかし、基本をつくっても、現実の経営はそれを越える「複雑性」をもっている。どうしても基本は一般化したもの、抽象化したものであり、現実のもつ複雑性に対応できないことが多々ある。
3 基本をつくる!
・スモール・ビジネスの経営は小さいために大企業とちがって、なんとなく外から見えるような気になる。しかし、八百屋以外でも実際には見えない部分が多く、そこにそれぞれの経営の基本がかなり存在している。それを明らかにするのがわれわれ経営学者の責務であるが、スモール・ビジネスのビジネス・パーソンもその基本を整理し、習得することが企業としての継続を可能にしていくことであろう。
永続的成長企業ネットワーク 理事
横浜市立大学名誉教授 斎藤毅憲
- 開催日2018年11月5日
- 場所
- 時間
- 費用