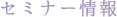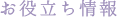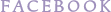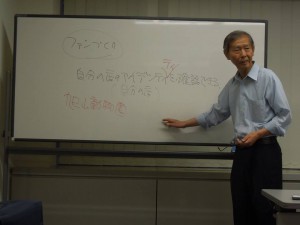永続的成長企業ネットワークの第5回講演会は6月17日に、横浜市立大学名誉教授の斎藤毅憲氏を迎え、商店街の活性化の最近の状況について講演を行った。(続き)
概要は次のとおり。
■研究のイメージ
■平成25年度神奈川県商店街実態調査速報から
■商店街の衰退要因
■衰退の間接的要因
■衰退の直接的要因
■衰退のステイクホールダー(利害関係者)別分析____↑(前回)
■酒店街活性化の試み
◆“空き店舗”対策
◆朝市
◆一店逸品運動
◆イベントの開催
◆パートナーシップのなかの商店街
◆環境変化への対応
◆ちょい呑みフェス
◆注目すべき事例
■おわりに_____________________↑(今回)
■商店街活性化の試み
イノベーション(改革)とリノベーション(改善)の区別はなかなかはっきりしませんが、、比較的大胆な改革と比較的小さな改善の試みを総合的に見ていきますと、つぎのようです。
◆“空き店舗”対策――空き店舗とか、シャッター通りと言っている。空き店舗は歯が少し抜ける、しかしシャッター通りになるともう少し歯が欠けてきてずいぶん店がなくなったという感じでしょうか。あとは更地化です。空き店舗というのは、まだいいのかもしれない。1,2店あいたからちょっと埋めればいい。シャッター通りになるとかなり苦しいなと思う。さらに更地化は深刻化で、ただ地方では住宅地も更地化しています。
空き店舗の対策として、学童保育・高齢者向けサービスの拠点化、アートの展示ゾーン化やカルチャー・センター化、店舗経営を若者などに体験させる場、産品の売り場などがあります。
◆朝市――神奈川では「かながわ朝市サミット」が結構成果を上げているようです。しかし、朝市はある程度出店数がないと、なかなか認知されず、集客ができないということがあります。大学での朝市については、横浜商科大学で実施しています。
◆一店逸品運動――個店の逸品をつくるとか、発見するとか、そして、何もないところでは商店街でブランド商品をつくろう、という動きは結構行われている。
◆イベントの開催――文化系のイベントは多いが、スポーツ系は少ない。横浜の場合は商店街プロレスが知られている。またJリーグ・サポーターのための場として、特に飲食店が利用されています。選挙に行こうぜ!キャンペーンといって選挙に行って、投票証明書をもらい商店街で安くサービスを受けるというのがあります。このほかに「おみせサンタ」「合格祈願」などいろいろ理由をつけてイベントをやっています。「観光地型」の商店街―湯河原とか熱海―も面白いイベントを実施しています。あとは著名な商店街へのツアーなどが行われています。ただイベントは外部からは人は来て賑わいはつくられるが、あまり収益の増加にはなっていないという評価もあります。
◆パートナーシップのなかの商店街――商店街間の連携、例えば六角橋の商店街と川越の商店街が連携することもあります。地域を越えてやっていることが分かります。商店街と行政の協力は当然で、あとは学校と商店街の連携が結構行われています。小学校とか大学と商店街の連携が結構実施されています。
◆環境変化への対応――高齢化対応で御用聞きの再生とか、情報化対応でインターネットを活用して店舗・商店街のアピールを行っています。安全性・快適性を重視した環境対応では駐輪場・防犯活動・安全安心フェスタ・AEDや防犯カメラの設置・子育て女性への配慮(元町商店街)などが行われています。さらに、地域衰退対応としては、地域資源を活用して商品開発やブランド化を図るという動きが結構行われています。どこも非常に熱心にやっていて、本当に成功するかどうかはわからないが、努力は非常にすごいものだと思っています。あとは、グローバル化対応―神奈川の商店街の大きな特徴かもしれないが―外国人が非常に住んでいるということで、国際色豊かな雰囲気の商店街が形成されています。川崎市の桜本商店街といえばキムチで有名で、大和市の二条通りは東南アジアの人々が多く住んでいます。神奈川の場合は外国人が多く住んだがために、それに対応するような商店街になっています。
◆ちょい呑みフェスの――場所によっては「バル(スペイン語の酒場)」「はしご酒」ともいっています。「ちょい呑みフェス」が、最近神奈川県内の飲食店の間で行われ始めている。飲食店同士のコラボは、これまであまりなかったのではないかと思っています。飲食店の間で、特に商店街の若手の青年部の人たちが頑張ってはじめています。一般的な事例としては、3枚つづりのチケット(2,500円)を購入して、好みの店舗に出向いて「はしご」をして歩く。1枚につき、ドリンク1杯と自慢の料理1品を楽しめることになっています。利用者は割安に飲食でき、店舗には新しい顧客が獲得でき、そして商店街は全体として賑わいができ活性化できる、という「三方よし」になっています。ただし、これを成功させるためには、ある程度の店舗数が参加してくれることが必要となります。多くの店舗が参加して利用者が自由に選べる雰囲気をつくらないとあまりうまくいかないものでしょう。
◆注目すべき事例
まちゼミの実施を注目しています。愛知県岡崎市はパイオニアで、それが全国的に広がってきています。秋田県能代、山形県米沢、長野県松本、千葉県松戸、東京都青梅、静岡県焼津、三重県松阪、福井県の小浜、島根県松江、あちこちでまちゼミが始まっています。神奈川県の中でも、横浜中華街―これは中華街がではなく横浜商科大学がやっている―、横須賀、秦野、川崎でも行われています。このまちゼミのポイントには、①ファンづくりに徹する。②自店舗で実施する。③講義だけでなく、体験などをミックスさせ、1時間ぐらいにする。④開講期間は1か月から1か月半くらい。⑤ある程度の店舗に参加してもらい、周知を図る。⑥原則として無料が望ましく、受講者は少数にする。⑦PRはチラシなどを利用する。⑧修了後、反省会・報告会を実施するなどがあるといわれています。
三重県松阪市の事例―ある茶舗では―、講師は店主で、お茶に含まれる栄養素など基本的情報を教えるほか、おいしいお茶の入れ方を1時間の無料講座で丁寧に見せている。 まちゼミでは売るということは目的でなくて、そのお店と主力商品の説明とそれにかかわる基本的情報の提供に徹しています。絶対に売るということは言わない、どうしたらお茶は旨く出せるのか、どうしたら旨く飲めるのか、そしていろんな使い方も教えてくれるというものです。
私は、商店街の活性化を考える上で、まちゼミは非常に良いものではないか、と考えています。ファンづくりということとならんで、お店にとっては、自分の店のアイデンティティ(自分自身)を確認できる、うちの店はこういう店だったという、わかりきっていることだが、この忘れていたことを確認できるということです。そして、自分の店がこれまでなんとか経営を続けてこれたことを確認する場になるんではないかと思います。私は、ファンづくりは当然これからも大切なことだが、店主にとっては自分の店のアイデンティティを確認できるチャンスになっているのではないかと思います。おそらくただ漫然と商売を行っている人が多いのではないか。先代はどうやってお客を獲得し、今はどうなっているのか、反省する場にまちゼミはおそらくなるのではないか。私は、まちゼミに商店街活性化のためのヒントを得たいと思う。
■おわりに
旭川市の旭山動物園の再生に関するレポートを最近読みました。私はここにも商店街活性化に関わるようなヒントがあると思っています。動物園はあまり面白いところではない。だから入園者が集まらない。動物園の動物は大体いつも寝ている、そして入園者に背中を向けている。動物らしい生き生きしたところが全然ない。そこで動物園は全く魅力がないものになっていたわけです。おそらく商店街もそうなっているのではないか。
旭山動物園の再生の方法は、動物を入園者の目線に向かわせています。いわゆる利用者に向き合うようにしています。飼育係も動物もお客さんに向く。商店街もそうであるし、かつての旭山動物園もそうであったが、利用者に向き合うという視点が非常に少なかったかと思っています。旭山動物園の1番の改革は何かというと、いろんな設備を変えたということもあるが、結局「ワンポイントガイダンス」これを飼育係が入園者に向かって行った。従来飼育係は自分の担当する動物を飼育していればいいんだ、お客とは関係がないのだと思っていました。それではダメだとし、一番欠けているのは入園者の方を向いていなかったとし、動物の本来持っている姿を入園者に見せなければいけないと考えるようになり、飼育係が動物と一緒になって入園者に説明するようになった。それでお客が入ったというのです。私はこれだと思います。商店主は利用者に向き合ってこなかったのではないか。旭山動物園もそうだった。やはりお客さんに向き合うことによってはじめてお客が帰ってきた。これが原点ではないのか。
もう一回、まちゼミみたいなもので、商店主はお客さんに語り、説得する。それが一番大切なことと思っています。ただ商店主もただ作ればいいといった農業の従事者と同じようにただ商品を並べていればいいんだでは経営はないということです。経営はなしで、作ればいいというのと同じように商店街も品物をならべれば、買ってくれるだろうという発想が無理なんだろう。
もう一回小売りの原点に立ち返る必要があるのではないか。そうすれば、そんなに大再生はできなくても、今よりは何とかなるのではないか。その原点はやはり旭山動物園で飼育係が動物と一緒になって入園者に顔を向けるように動き出した。私はこういうことが必要なんではないかと思う。あとは動物の持っている生き生きしたところを動物園が見せた。商店街もそういう要素が必要なのかもしれない。そして、いままで言われてきたように生鮮3品のお店がなくなると、商店街が衰退するといいます。八百屋さん、魚屋さん、肉屋さん―一番元気な商売をしていた人たち―がいなくなると、それぞれの個店が行う生活の一番底辺の食の部分を支えてきたわけですが、そういう要素をどうやって取り戻せるのか。それが商店街活性化のヒントとして非常に大事ではないか。
さらにアクティブなリーダーの重要性のほかに、ヒトの問題では「よそ者・若者・ばか者」が重要といわれるが、基本的には今やっている方策の中で、私は意外とまちゼミみたいなものが一番原点になるのではないか。やはりもう一度お客さんと向き合おう、という感覚を取り戻すことが必要ではないか。結局のところ対面販売といいながら、そうではなくスーパーマーケットと同じ売り方になっていると思っています。
- 開催日2014年6月17日
- 場所-
- 時間-
- 費用-