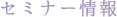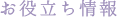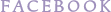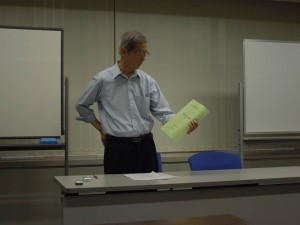永続的成長企業ネットワークの第5回講演会は6月17日に、横浜市立大学名誉教授の斎藤毅憲氏を迎え、商店街の活性化の最近の状況について講演を行った。
概要は次のとおり。
■研究のイメージ
■平成25年度神奈川県商店街実態調査速報から
■商店街の衰退要因
■衰退の間接的要因
■衰退の直接的要因
■衰退のステイクホールダー(利害関係者)別分析_____↑(今回)
■商店街活性化の試み
◆“空き店舗”対策
◆朝市
◆一店逸品運動
◆イベントの開催
◆パートナーシップのなかの商店街
◆環境変化への対応
◆ちょい呑みフェス
◆注目すべき事例
■おわりに_____________________↑(次回)
■研究のイメージ
関東学院大学経済学部が文科省からいただいた3年間のプロジェクト研究で県内の中小企業の研究を行っています。私は関東学院を辞める最後の年でしたが、あまり研究してこなかった商店街の調査をやってみようということになりました。そして、この2年間資料集に近い報告書をつくってきました。さて、研究のイメージとして活性化している商店街には、アクティブなリーダーがいるのではないか。このリーダーが商店街の内部をまとめている。いわゆるすぐれたリーダーの存在、その優れたリーダーは商店街をうまくまとめあげています。
もう一つ考えておきたいのは、このリーダーのもと、外部に対してオープンシステムになっているのではないか。非常に開放的で、いろんな人を受け入れるような素地があるのではないか。外部資源を取り入れて、パートナーシップを組んで何かやるような商店街になっているのではないかと考えています。
リーダーの存在。リーダーは商店街の内部をうまくまとめあげる。それと外部にもオープンで、外部のステークホルダーに対しても、非常に柔軟に対応してかれらの持っている資源を活用して何か新しいことをやろうとしているのではないか。これらが研究のイメージになっています。
■平成25年度神奈川県商店街実態調査速報から
商店街の衰退が下げ止まったかもしれない、底を打ったかもしれない。調査速報から、「景況感」で繁栄しているが前年の1%が3%に増えている。回復してきているが5%から8%に増え、衰退しているは32%から29%に減る、という景況感になっています。今後の活性化の見通しについては、益々発展するが1%から3%に増えています。やり方次第で活性化できるは前年と同じ28%とですから、ほぼ3分の1の商店街がいい見通しを出している。どうやっても衰退するは20%から15%に減っています。
このデータをどう読むかということについては、商連かながわのあるトップから、少し良くなって下げ止まったのかな、という話を伺ったわけです。私はそうではなくて、2極分化が進んでいるのではないかと思っています。結構頑張っている商店街とダメなところがハッキリしてきたのかなと思っています。ただし、全体としては矢張り衰退傾向にあることには変わりがないのではないか。
■商店街の衰退要因
・商店街の形成と発展については、大都市では、明治末期から大正、昭和の初期に形成されて、商店街組織みたいのができあがっています。私の実感としては、第2次大戦後の昭和20年代から30年代にかけて商店街が発展し40年代がそのピークになるのではないか。50年代はまだ、はっきりとした衰退傾向は出ていないかもしれないが、大型量販店の台頭などによって少し陰りが出てくる。横浜市内・神奈川県内の新聞記事などを集計してみると、昭和40年までは良かったよね、というのが大体の書きぶりになっているようで、そんな感じを持っています。
おそらく昭和20年代から30年代になぜ商店街が発展したかというと、企業などへの就職は困難であったのです。自分で何か商売をする、なにかあるものを売るという感じで自力で仕事をせざるを得なかったことがあります。そして小売業のコアは、対面販売型の業種中心の小規模個店が前提になっています。横浜市の大口通りの商店街は、1946年には相当のお店があったということがわかっていますがそれがだんだん減っていくわけです。ここで業種というのは、商品の名を被せた商店のことで、八百屋さん、魚屋さん、時計屋さん、電気屋さんはその例になります。
■衰退の間接的要因
・高度経済成長期に日本の企業が発展して労働吸収力が増えて、第1次産業従事者とか自営の商業者が減って吸収されていく。大都市では企業が発展して多くの労働力を必要としたということです。
・大都市への人口の集中化がすすみ、大都市の過密化と地方の過疎化の問題が出てくる。商業の発展は人口問題でもあり、いくら頑張ってみても人口がいなければ地方の商業は成り立たない。ある程度の人口がなければ商業の発展は難しいのではないか。
■衰退の直接的要因
・流通革命と新業態の台頭――昭和30年代の後半から流通革命、アメリカの大量生産が可能になって、それを大量消費に結びつけなければいけないということで、流通のチャネルの改革を行わねばならないというのが出てきた。それと並んで、アメリカ流のスーパーマーケットという新業態が台頭する。ここで業態という言葉を使っているが、業態というのは、よく知られているように売り方を中心とした考え方です。スーパーマーケットはセルフ・セレクション、自分でお店に行って自分で商品を選んでくる。それは対面販売ではない。地方においてもスーパーマーケットが台頭する。その中で、大手のナショナル・チェーンへと発展していくものもあらわれる。そして、大手のナショナル・チェーンへと発展したスーパーマーケットは、さらに全国展開をするようになる。ダイエー、イト―ヨーカ堂などを中心とした新業態が台頭して、それが地方にまで進攻し、全国制覇を試みる。このことによって、地方の名門百貨店が凋落するだけでなく商店街にマイナスの影響を与えることになります。
・モータリゼーションの進展――これによって地域の商業構造が大きく変化してしまった。自動車により、広域移動が可能になって、市街化地域が拡大する、商業ゾーンが郊外までつくりあげられていく。他方メイン・ストリートは駐車場を持たないために限界を示すことになります。こういうモータリゼーションによって幹線道路沿いにロードサイド店が展開されます。
・業態間の競争関係の激化――いろんな業態が小売り分野に参入してくる。そして競争が激化する。スーパーマーケットのあと、コンビニエンスストア、ホームセンター、ドラッグ・ストア、業種別量販店(電気製品・書籍・ファッション・アパレル系などの専門店)、大型複合施設、ネット販売、地産の産直店など、の様々な業態の出現で、商店街がそのようななかで埋没せざるをえない状況が作り出されてきたわけです。要するに、スーパーマーケットの台頭、モータリゼーション、いろんな業態が台頭してきて、商店街は衰退せざるを得なくなったのです。
■衰退のステイクホールダー(利害関係者)別分析
・商店街自体については、経営上の限界(経営資源の不足、経営戦略の欠如)を持っていた。その結果、大型店や新業態対策に有効な対抗策を見いだせなくなりました。経営不振がもたらす悪循環により経営マインドがわるくなっていった。しかも商店主の職住分離が進み、商店主がお店で生活をしなくなり、地域密着の度合いが非常に減ってきたわけです。それから、いわゆる「後継者問題」もあります。
・行政(地方自治体)は、商業開発政策で失敗をした。町の発展だということで、どんどん大手の商業施設を誘致する。いまだに大型商業施設をつくらせる自治体がある。もうそんな時代じゃないのにまだやっています。町の発展を建前にした単純な商業拡張主義が横行していたのではないか。おそらく横浜だって、あれだけMM地区に商業ゾーンをつくれば、伊勢佐木町の商店街がダメになるのは当たり前なのだが、おそらくは単純な商業拡張主義が横行したんではないかと思う。その結果オーバーストア的状況が作り出されて商店街が衰退せざるを得なくなったわけです。
私は自治体の商業開発政策をしっかり検証する必要があるのではないかと思っています。
・消費者の「商店街ばなれ」が生じ、消費者は新しい業態の方に魅力を感じてしまっています。そして商店街は高齢者だけのものになってしまう。
・新業態の小売業はかなりアピール度が強い。その結果消費者の支持を獲得してきました。ただし、地域密着性の面ではかなり問題があります。利益が上がらなくなると撤退してしまう。全社的経営戦略の一環で撤退してしまい、買い物難民なども生じている地域が発生しています。 (続く)
- 開催日2014年6月17日
- 場所-
- 時間-
- 費用-