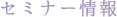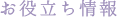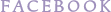セミナー報告】
[見学記] その(2)/3回連載
第11回職欲(ジョブヨク)の未来@ヨコハマスペシャル
――平成29年7月22日 富士通エフサス――
永続的成長企業ネットワーク理事
横浜市立大学名誉教授 斎藤毅憲
・最後のセッションⅢは、他国に学ぶという姿勢のもとに、日本の組織やベイスタービールがとり入れるべき新しい働き方や制度を考えてもらうことをテーマに討論が行われ、各グループはまとめを発表している。それは、また自分にとっての理想の働き方を語る場となったと思っている。
・企画グループは、最終的にどのグループのまとめがいいのか、参加者などの投票によって決定し、発表していたが、どうしてもアピール性のあるまとめ方をしたグループが第1位となっている。
・全体的にみると、ネガティブ・イメージの強い現状の雇用制度(システム)を緩和したいという考え方が強くなっていることがわかる。フレックスな制度を求める意見が多く、テレワーク、完全フリーランス雇用、育休・有休の100%消化(男性を含む)、残業ペナルティ制、子どもや猫同伴の仕事空間づくり、子育てができる職場など、自由な働き方をもとめる提案が行われている。雇用制度をある一定の枠組のなかでつくりあげるのではなく、かなりの多様性のなかで考えていくべきであるという。これは実際もっともな主張であり、企業の経営者や人事担当者には真剣にとり組んでほしい問題である。いつまでも長時間労働を強いる経営であってはならない。そして、働く人びとにとっての“やさしい”余裕のある経営を行ってほしい。
・第2に、発表のなかではあまり明示的にはなっていないが、参加者にとって割りあてられた仕事は当然のこととして、しっかり遂行できるとか、遂行していることを前提にして議論しているように思われたことである。つまり、「仕事できない自分」とか、「そのような他人」が参加者にはあまりイメージされていなかった。ネガティブ・イメージの雇用制度が問題のコアであり、働く側には問題がないように思われた。参加した大人は、仕事の遂行能力の高い人びとであり、学生も仕事のできない自分をイメージしていないという印象をもった。
・変化の時代なので、仕事の内容が急拠変ったり、むずかしくなることもありうる。そして、これまでにコンタクトのない対外的な利害関係者(ステイクホルダー)の調整にも神経を使うようになっている。そこで、新人社員だけでなく、キャリアのある人間でも一時期にせよ仕事ができない状態に陥るおそれがある。その意味でも働く人びとにとって“やさしい”余裕のある働き方が必要であると私は思っている。「長期にわたる仕事上の無能(仕事ができないこと)」はゆゆしきことであるが、人事異動によって仕事上の無能に一時期であってもなることは多い。要するに、人と仕事の関係をどのようにするかについては、もう少し考えることがあると思われた。
・第3に、必ずしも多くなかったが、これまでの日本人の働き方の良さを認める発表が行われている。すでに述べたように、長所の指摘は少なかったが、まったくなかったわけではない。現状はきびしい働き方ではあるが、職場には暖かい雰囲気も残っているし、チームワークを大切にし、職場の仲間どうしが相互に支援するような企業文化も完全に消失しまったわけではない。
・また、能力主義といわれる反面で、年功制や和を重視する集団主義の要素がきれいさっぱりなくなったとはいえず、「中間的なあいまいな折衷主義」のようにも見える。したがって、この辺の詳細な分析が求められている。年功制や集団主義を純粋に信じている人はいないであろうが、しかしそれでは能力主義100%かというと、それも信じがたいと思える。(以上「その(2)」)
- 開催日2017年7月22日
- 場所
- 時間
- 費用