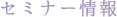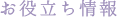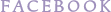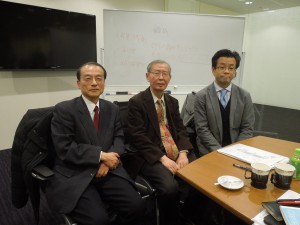永続的成長企業ネットワーク企業である「アーバン・コーポレーション(株)」の経営幹部・幹部候補者に対し、『UC(アーバン・コーポレーション)・ MBAセミナー』として第4回目を開催しました。(全6回予定)
1 開催日 平成29年2月16(木)
2 会 場 アーバン・コーポレーション(株)
3 参加者 11名(受講者8名(業務出張のため1名欠席)と塾長・講師・助言者)
4 テーマ 【第4回】「組織のかたちをどのように考えるか。」
5 主な内容
・第3回までは、戦略を考え、戦略づくりと進んだが、今回は組織をつくることを考える。「戦略が組織を決める」「組織(構造)は戦略に従う」組織図をつくる。人を配置する。自社の組織図はどのようになっているのかを問題にするという命題を前提とする。
・組織づくりの考え方
☞組織成立の3要素―共通目標、貢献意欲、コミュニケーション、の3要素が揃ったとき、協働の体系としての組織は成立する。
☞組織構造を決めるもの―組織における分業と調整の枠組みを「組織構造」と呼ぶ。
分業関係と専門化:仕事を分割し、担当者を決める。分業によって能率と生産性は向上する。
部門化:役割どうしを結びつけてグループとして括る。組織図にあらわされる。
公式化:仕事を標準化する。マニュアル化。
階層化:タテの関係をつくる。部下の数が増えると階層はフラット型になる。部下の数が少ないと階層はトール型になる。現在の議論では、フラット型が望ましい。
☞組織の管理原則―組織づくりのための基本原則。
命令一元化の原則:ひとりの上司からのみ命令をうける。命令の出所が複数であってはならない。
統制の範囲の原則:上司が統制できる部下の数を「統制の範囲」とよぶ。上司の能力、部下の成熟度、仕事の内容などによって統制の範囲は変化する。一般的に一人の上司が直接管理できる人数は、5~7人程度(スパン・オブ・コントロール(span of control))。
権限と責任一致の原則:権限と責任は一致しなければならない。
専門化の原則:仕事を分割して、ひとりがひとつの仕事を専門的に行う。
階層化の原則:職能は垂直分化し、階層化される。
権限委任の原則(例外の原則):ルーチンワークは、できるだけ部下に権限を委任する。上司は権限を委任しても、それで終わりでなく監視する権限を有する。部下は上司に報告義務がある(アカウンタビリティaccountability)。報連相とは上下関係を指す言葉である。
・組織の基本形
☞職能部門別組織:水平的に分化した職能別に部門化を行ったライン・アンド・スタッフ組織の形態。スタッフは直接企業利益に結びつかない活動をいう。大企業ではスタッフが大きくなり、権勢をふるうこともみられる。
☞事業部制組織:事業部(division)は、軍隊用語で師団を指し、師団は単独で作戦実行を行える組織単位。事業部はある意味、会社の中に会社がある自己完結的な単位。各事業部は利益責任単位(プロフィット・センター)。コスト・センターではない。
・組織の実行性の向上
☞現代はフラット化とネットワーク化の時代でもある。
・創業25年(2月14日創立25周年記念祝賀会開催)。成長著しいアーバン・コーポレーション(株)の組織について、受講者が現状、課題、展望を本音で語り、深い議論が行われた。
・斉藤講師から講義のほか、人事異動には活用型(企業側の立場)と能力開発型(若手の育成)があり、人事は安定的に行わなければならないが、短くなる傾向もある。
部下の人数(スパン)を考えるときに、重要なのは部下の仕事の成熟度が大切である。
当社の組織は事業部制組織のかたちをとっている。
当社の社員の離職率が同業他社より非常に低いのは、組織文化(カルチャー)が良いあらわれである。などの補足があった。
[使用テキスト:斉藤毅憲編著『経営学を楽しく学ぶ』(Ver.3) 2012年、中央経済社]
(文責:塾長 吉田正博)
- 開催日2017年2月16日
- 場所
- 時間
- 費用