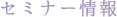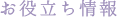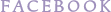【誌上テーマ別サロン】第45回
<基礎講座>
小規模企業の振興
―「中小企業経営学入門」(45)―
1 地域の衰退要因としての小規模企業の減少
・人口の減少や若者の流出だけでなく、小規模企業の減少が地域の衰退を招いていることは確かである。国も成長志向のある経営マインドが積極的なスモール・ビジネスは支援するが、競争力がないとか、変化への適応能力のないスモール・ビジネスの退出に仕方がないと考えていたのかもしれないが、その減少はきびしくなっている。総務省のデータによると、1999年のわが国の中小企業数は484万社で、そのうち小規模企業は423万社(87%)であったが、10年後の2009年にはそれぞれ、420万社、366万社(87%)となり、減少数は64万社、57万社(減少率はいずれも13%)になっている。これを従業員でみると、99年に3,120万人のうち小規模企業は1,098万人(35%)であったが、10年後には2,834万人、と912万人(32%)に減少している。中小企業全体では285万人(9%)の減であるが、小規模企業に関しては186万人(17%)の減少になっている。
・これによると、単純に計算すると、小規模企業は全国で毎年約6万社弱づつ減少している。そして働く人間については、約19万人平均の減少になっている。
2 国の方針変更
・このような小規模企業のきびしい実状を改善するために、国は2013年9月施行の中小企業基本法を改正し、小規模企業の意義を明確にしている。それによると、「地域経済の安定と経済社会に発展に寄与」することに小規模企業の意義を規定し、小規模企業の活性化、成長発展に対応した支援などを明記している。
・これをうけて、2014年6月には「小規模企業振興基本法」が施行されている。これまでの成長・発展だけでなく、小規模企業の「事業の持続的発展」を積極的に認めていくことが規定されている。そして、国、地方公共団体、支援機関などの相互の連携や協力に関する責務も規定されている。あわせて、国は政策の継続性・一貫性を担保するための小規模企業振興基本計画を策定するものとしている。
3 商工会議所などによる支援機能の充実
・「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」も、2014年9月に改正されている。需要開拓や承継問題などをめぐって事業計画の策定や実施などを小規模企業に寄り添って支援すべきことを明示している。要するに商工会議所などの役割の強化がはかられることになった。
永続的成長企業ネットワーク 理事
横浜市立大学名誉教授 斎藤毅憲
- 開催日2018年7月5日
- 場所
- 時間
- 費用