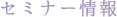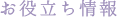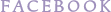【誌上テーマ別サロン】第37回
<基礎講座>
スモール・ビジネスと生産性(2)
―「中小企業経営学入門」(37)―
1 多い「労働集約型」という特長
・スモール・ビジネスは、経営資源(特に資金)の制約や地域の小さな市場を目ざしているために、巨額の設備投資を行うことはむずかしい。ということは、いわゆる「資本集約型」といった多額の資金を投下するという意思決定はやりにくいことを意味している。むしろ機械設備にお金をかけるよりも人手に頼ることになるので、スモール・ビジネスは「労働集約型」の経営をとらざるをえない。この高い労働集約性は生産性の低さにかかわるとみられてきた。
2 人手依存の内実
・それでは、労働集約型経営における人手依存とは、どのようなものであろうか。これには専門的な技能や熟練を要するものと、単純労働的なものに大別できると思われる。専門的な技能や熟練を要するものは、機械に代替できないので、その担当者に対する評価は高くなる。正規社員としての雇用が一般的であり、報酬も高くならざるをえない。これに対して、だれもがいつでもこなすことができるような単純労働的なものの評価は必ずしも高くなく、担当するワーカーは非正規労働になる可能性きわめて高くなる。パートやアルバイトなども多く採用されている。
・個々の企業の事情によって、このふたつのタイプのバランスやミックスが決まると考えられる。人材として専門的技能や熟練を要するスモール・ビジネスの場合、つくりあげる製品やサービスの価値は高いが、市場は必ずしも大きいわけでないために、売上高は多くないかもしれない。したがって、必ずしも生産性は高くならない。これに対して、単純労働的なものを中心とするスモール・ビジネスの場合、提供する製品やサービスは相対的に多いが、価格面でみると高くないので、高生産性とは言えないであろう。
3 大企業の生産性との比較
・大企業の場合、大きな市場の獲得を目ざして、資本集約型の投資を行うことができる。そして、最新鋭の機械設備をとり入れれば、生産性は高くなる。また、売上高が好調で稼働率を高めると、コストは低減し、生産性は向上する。もっとも、競争がきびしく、技術の進歩も早いので、商品の陳腐化を心配しなければならない。くわえて、生産や販売に直接にかかわらない間接部門――実質的には戦略部門とサービス(支援)部門――のコストがかかり、その生産性が問題視されてきた。
永続的成長企業ネットワーク 理事
横浜市立大学名誉教授 斎藤毅憲
- 開催日2017年10月5日
- 場所
- 時間
- 費用