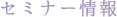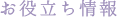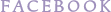【誌上テーマ別サロン】第36回
<基礎講座>
スモール・ビジネスと生産性(1)
―「中小企業経営学入門」(36)―
1 ターゲットとしての「地域市場」
・スモール・ビジネスが主要なターゲットとしているのは、地域市場(ローカル・マーケット)であり、立地している特定の地域の顧客を相手にビジネスを展開している。つまり、通常は地理的に近接している狭い地域の顧客を意識しているのである。あわせて、比較的大きな都市でもないかぎり、その市場はあまり大きくなく、顧客の数は少ない。そして、同じ地域に同業の企業が活動しているとすれば、獲得できる顧客の数はさらに制約をうけることになる。
2 不要な巨額な設備投資
・地域市場をターゲットにし、比較的少ない顧客を対象としたビジネスになるとか、そうならざるをえないとすれば、スモール・ビジネスの経営者は巨額の資金を使った設備投資を行う必要はないわけである。広大な土地を購入して、大規模な工場をつくり、最新鋭の機械設備を導入する必要はなく、市場規模にあわせた工場の開設でスタートすべきである。これがこの場合の合理的な意思決定(デシジョン・メイキング)というべきものであろう。いうまでもないが、顧客が少ないのに、大きな工場をつくることはできない。
・しかし、市場規模にあわせたために、工場は小規模となり、機械設備より人手に頼ろうとすれば、大量生産(マスプロ)による「規模の経済」は作用しなくなり、製品単位あたりの価格は上昇してしまい、どうしても生産性は低くならざるをえなくなる。スモール・ビジネスの“町工場”には、このような特徴がある。
3 無意味な大企業との比較
・以上のように、スモール・ビジネスにおいては生産性が低く、能率はあがらない経営が行われている。そして、大企業のような巨大な市場を意識した量産体制はとられておらず、規模の経済も作用していないのである。
・だが、まったくちがった状況のもとで活動している大企業と比較して、スモール・ビジネスの生産性を議論することに、どのくらいの意味があるのであろうか。スモール・ビジネスには、小さいがゆえの経営のあり方があり、それは大企業のものとはちがうということをしっかり認識する必要がある。単純な比較を行い、スモール・ビジネスの経営は大企業にくらべて劣位にあるということには疑問を感じる。
永続的成長企業ネットワーク 理事
横浜市立大学名誉教授 斎藤毅憲
- 開催日2017年9月5日
- 場所
- 時間
- 費用