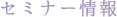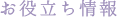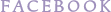【誌上テーマ別サロン】第35回
<基礎講座>
スモール・ビジネスの経営は劣っているのか
―「中小企業経営学入門」(35)―
1 「生産性が低い」との批判
・スモール・ビジネスの経営について、よくいわれる批判に、「生産性(プロダクティビティ)が低い」がある。大企業とちがって、生産性が低く、能率があがらない。そして、賃金水準も高くないという。また、これらを納得させるようなマクロ的なデータも公表されている。
・小さくて、安定しておらず、環境の変化への対処能力もないので、弱いという目でスモール・ビジネスはみられている。さらに、いま述べた生産性も低く、俸給も低いので、安定志向の学生には就活の対象にならないことになる。創造的であるかどうかはわからないが、安定志向の学生は成績優秀者でもあるので、スモール・ビジネスには成績優秀者が集まらないという風にもみられているかもしれない。
2 「スモール・ビジネスの経営は劣っている」というステレオタイプ
・このようなスモール・ビジネスの弱点に着目すると、どうしてもスモール・ビジネスの経営は大企業に比較すると、劣っているというステレオタイプ(固定観念)が定着しているのも、あたり前のことと思われる。そして、小さな企業はダメな経営を行っていると長い期間にわたって考えられてきたといえる。
3 スモール・ビジネスから成長してきた「大企業」
・スモール・ビジネスと大企業との間には、経営上の格差があり、大企業の経営は優秀で、スモール・ビジネスのそれは劣っていると考えられてきた。これをとりあえず「大企業のスモール・ビジネスに対する経営優位説」と名づけるとすれば、この優位説が暗黙のうちに経営学では支配してきたといえるであろう。
・大企業は誕生当時から大企業ではなく、おおむねスモール・ビジネスから出発している。そして、スモール・ビジネスが成長することで、大企業に変わってきた。成長の源泉は経営が優秀であることであり、その結果(アウトカム)が成長であるので、この面からみても大企業の経営優位説の妥当性が認められてきたといえる。
・もっとも、経営学は成長してきた大企業の経営を主にとり扱ってきたので、小さな企業の経営に関心がなく、無知であったことも正直にのべておく必要がある。
永続的成長企業ネットワーク 理事
横浜市立大学名誉教授 斎藤毅憲
- 開催日2017年8月5日
- 場所
- 時間
- 費用