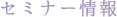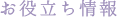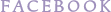【誌上テーマ別サロン】第32回
<基礎講座>
かえがききにくいスモール・ビジネスの経営者
―「中小企業経営学入門」(32)―
1 スモール・ビジネスにおけるヒューマン・リソース(人的資源)
・昔から「企業はヒトなり」といわれてきた。要するに、企業にとって人材、つまりヒューマン・リソース(人的資源)がとくに重要なのである。これは大企業だけでなく、スモール・ビジネスにとってもいえることである。とくにスモール・ビジネスにおいて働く人びとが少ないので、1人1人の果たす役割とポジションは大きい。すでに別のところで述べたが、1万人の大企業と10人が働くスモール・ビジネスではそれぞれの人間は等しく重要であるが、小さな企業では1万人分の1ではなく、10分の1なのである。
2 最大の経営資源である「経営者」
・スモール・ビジネスでは、それぞれのヒューマン・リソースがもっている能力やスキルを発揮しなければならない。いわゆる“お荷物”になり、企業や同僚の足を引っぱる人間は不要なのである。そして、スモール・ビジネスの経営者は最大の経営資源として企業の生存と継続にかかわっている。経営資源が必ずしも十分でなく、不足している状況のなかで、経営者はこの不足にめげずに活動し、それを克服しているのである。
3 「困難な代替性」を特徴とする経営資源
・要するに、スモール・ビジネスのヒューマン・リソースのなかで、とくに経営者(社長と周辺の側近)は、かえがききにくいという代替性が困難な経営資源である。若い起業家のなかにはある程度成功したところで、その企業から離れていく人も見られるが、スモール・ビジネスの経営者は比較的長期にわたって、そのポジションを守り、活動している。普通のサラリーマンであれば、とっくに退職している年齢をすぎても一線で元気に活躍している。
・一部では当然のことながら、やめないために困った老人とも見られているが、やめないし、そしてやめることができないのである。かえがいてもやめないのかもしれない。しかし、かえがいないために、やめることができなくなっているともいえる。
・オーナーでもあるスモール・ビジネスの経営者に引退の鈴(スズ)をつけられる人間は社内にはいないであろうが、かえがききにくい経営資源であることには変りはない。うまく後継者を育成し、バトン・タッチしていくことが望ましいが、それがうまくいかないのも現実のところであろう。そこで、かえがきく後継者の発見や育成が大切になる。
永続的成長企業ネットワーク 理事
横浜市立大学名誉教授 斎藤毅憲
- 開催日2017年5月5日
- 場所
- 時間
- 費用