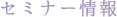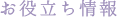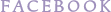【誌上テーマ別サロン】第31回
<基礎講座>
「信用づくり」とスモール・ビジネス
―「中小企業経営学入門」(31)―
1 スモール・ビジネスにおける信用不足
・スモール・ビジネスには、いろいろな欠陥というか、短所があるという。そのなかのひとつに「信用不足」があるかもしれない。著名な大企業で、それなりの業績をあげている企業の信用度は高いのに対して、どうしても小さな企業の信用は低いといわざるをえない。
・小さな企業にはヒト、モノ、カネ、情報といった経営資源が十分でなく、不足していると思われているから、信用がないのは当然かもしれない。いわゆるステイクホルダー(利害関係集団)は、経営資源が不足しているために、スモール・ビジネスに対して不安な気持ちをもっていることが多い。取引業者は取引の安定的な継続ができるかを心配しているし、資金を貸出す金融機関は返却がしっかり行われるかどうかを懸念している。また、採用される人間は、売上があがらないために、報酬が減額になるのではないかとか、悪い場合には雇用も失われるのではないかと勘ぐってしまうのである。
・このようなスモール・ビジネスに対するステイクホルダーの不安な気持ちが信用不足という状態を生みだしており、それはスモール・ビジネスにおける経営資源の不足を原因にしているとみてよい。
2 信用づくりの視点
・信用がない状態から信用される状態を変えるという「信用づくり」のためには、どのようにしたらよいのであろうか。これまで述べてきたことからいえば、不足している経営資源を改善していくことが大切になる。しかし、結論からいえば、それは一朝一夕にうまくいくことではない。むしろむずかしいことである。
・そこで、ここで大切になるのは、経営者をはじめとするヒューマン・リソース(人的資源)が日々の活動を誠実かつ真摯に見えるかたち行っていくことである。これによってステイクホルダーからの評価や賞讃をかちえていく以外には道はないのである。要するに「まじめさ」の可視化が大切なのである。
3 日常活動の可視化の継続
・要するに、日々の活動を誠実かつ真摯に見えるかたちで遂行することが信用づくりにつながるのである。しかも、それを愚直に継続していかなければならない。手を抜いたり、不正を行うと、せっかくつくりあげた信用もあっけなく失われてしまうことになる。
永続的成長企業ネットワーク 理事
横浜市立大学名誉教授
斎藤毅憲
- 開催日2017年4月5日
- 場所
- 時間
- 費用