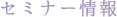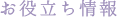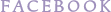【誌上テーマ別サロン】第30回
<基礎講座>
スラックのない経営をバネにするスモール・ビジネスづくりを!
―「中小企業経営学入門」(30)―
1 スラックの意味
・スラック(slack)はゆるいとか、ゆるみがあるという伸縮性をさしている。そこで、スラックのない経営とは、伸び縮みが少ないとか、できないような経営のことであり、弾力性の程度が低い、いわゆる余裕のない状態にある経営である。このような経営では環境における各種の変化に対抗できないわけである。そして、スモール・ビジネスには、このようなスラックのない経営というイメージがつきまとってきたように思われる。
2 経営資源の制約
・スラックのない経営の主な理由は、所有している経営資源によると考える。ヒト、モノ、カネ、情報などの経営資源が十分に所有されているわけではなく、むしろ不足しているので、いろいろな選択肢を考えたうえで、フレキシブルな動きをとろうにもとれないわけである。大企業においても経営資源は有限であり、無尽蔵ではないが、スモール・ビジネスの場合、この経営資源が不足しているという制約は大きいといわなければならない。そこで、とりまく環境のなかに、たとえビジネス・チャンスがあったとしても、それをいかすことができないことになる。
3 制約を克服する力の存在
・このようにみてくると、スモール・ビジネスはどうしても“弱い”存在というイメージでとらえられてしまうのである。しかし、生存と発展に強い思いをもつスモール・ビジネスの経営者はむしろこのような制約を克服しようとするエネルギーと知恵をもっていると考えている。それは、スラックのない経営であることを認めたうえで、これをバネにして制約の克服に立ち向っている。
・経営者は、スモール・ビジネスにとって最大の経営資源であり、“ないないづくし”のスラックのないなかで、このきびしい制約を克服しようとしている。そして、現代の日本においてはまさにそのような経営者や起業家の出現をもとめている。あわせて、そのようなヒューマン・リソース(人材)の育成を必要としている。これによって、“弱い”イメージをスモール・ビジネスはとり除いていかなければならない。そして、大学は大企業中心の教育を行っているが、スモール・ビジネスのための人材育成を行うことも期待したい。
永続的成長企業ネットワーク 理事
横浜市立大学名誉教授 斎藤毅憲
- 開催日2017年3月5日
- 場所
- 時間
- 費用