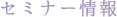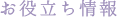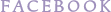【誌上テーマ別サロン】第27回
<基礎講座>
スモール・ビジネスにおける“スモール”とは?(1)
―「中小企業経営学入門」(27)―
1 公務員の賃金決定にかかわる企業規模とは?
・公務員の賃金決定については人事院または人事委員会の勧告が大きな意味を持っている。その決定は「民間準拠」といわれるように、民間企業のうち行政(役所の)組織と比較検討できるような組織の給与水準を参考にして行われてきた。かつては100人以上の従業員が働く企業が調査対象であったが、2000年代に入ってから、それが引き下げられ、60人以上になっている。
・行政組織は地方の自治体でも、組織の構造が階層分化と職能分化によってしっかりとつくられており、それに対応できる企業の規模は100人以上であったが、60人以上であれば比較検討が可能で、参考にできるということであった。これによると、60人以下の従業員数であればスモール・ビジネスであり、行政組織の参考にはならないことになる。
2 50人以下がスモール・ビジネスか
・かつて従業員が50人以上になると、別会社を設立するという経営者の話を聞いたことがある。50人程度までであれば、直接部下として管理ができるが、それ以上になると、できないのが、その理由という。いわゆる統制の範囲(スパン・オブ・コントロール)が最大で50人なのである。おそらく有能かつパワーフルな経営者であったと思うが、この話をうかがったときに、“スモール”の意味は50人以下のことか、と直感的に思った。それ以来、スモール・ビジネスの規模的なイメージは、資本金よりも従業員であり、しかも50人以下の企業と思うようになっている。
・社長と従業員が直接的にコンタクトがとれるのがスモール・ビジネスのコアと考えるようになった。もっとも、50人ぐらいになると、管理職の配置はどうしても必要となるから、管理階層ができはじめるとともに、職能分化も見られることになる。そこで、50人もかなり大きい感じがする。
3 特徴としてのオーナー型経営者の支配
・スモール・ビジネスの経営者は所有者(オーナー)であり、ほとんどがこのオーナー型経営者であることも特徴である。所有と経営が結合・一体化しているが、オーナーの人数は少なく、資本金もあまり多くない。まさにここにも“スモール”の意味がある。基本法では製造業で3億円までのものを中小企業としているが、300人と同じように、それは大きいという印象がある。
永続的成長企業ネットワーク 理事
横浜市立大学名誉教授・放送大学客員教授
斎藤毅憲
- 開催日2016年12月5日
- 場所
- 時間
- 費用