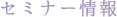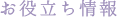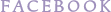【誌上テーマ別サロン】第26回
<基礎講座>
使用したくない用語としての「中小企業」
―「中小企業経営学入門」(26)―
1 広すぎる「中小企業」という言葉
・中小企業という言葉が使われている。しかし、広すぎるというか、大きすぎる感じがして、使いづらい。中小企業というと、中小企業基本法(1963年制定)の定義が常用される。1999年改定のものによると、製造業が資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業が1億円以下または100人以下、小売業が5,000万円以下または50人以下、サービス業が5,000万円以下または100人以下となっている。いずれも1973年の改定のものと比較すると、資本金規模が拡大している。
・この法律によると規模とくに資本金か従業員数によって中小企業の範囲をきめてきている。製造業の資本金3億円、従業員300名を例にすると、第一印象としてはかなり大きな企業であるように思われてならない。アメリカのスモール・ビジネス(製造業)の定義をみたときに、従業員500名が基準になっており、ずいぶん大きく、零細企業との差を感じたが、従業員の300名でも大きい。従業員数名から300名までを含むとすれば、かなりの拡がりがあり、中小企業といっても広すぎると感じてしまうのである。
2 「中小」を一緒にできないのではないかという疑問
・中小企業が文字どおり中企業と小企業からなるとした場合、規模的にみるとどのあたりにシキリがあるのであろうか。なかなかこのシキリを議論し、明らかにすることができない。小規模企業については製造業では20人以下、小売業・サービス業では5人以下と規定されているが、明確な根拠らしいものはないのかもしれない。
・これに関連して、問題となるのが、経営的にみると、小企業と中企業にはちがいがあり、おそらく中企業は小企業よりも大企業に近い経営を行っており、したがって小企業と中企業を一緒にして議論を行うことができないのではないかということである。つまり、中小企業を使うことには抵抗感がある。
3 小企業中心の経営学を!
・シキリの数字は未定であるが、中企業さらには中堅企業が大企業の経営に近いと考えるならば、中小企業ではなく、小企業の経営学の構築こそが求められるものになる。まさに小さな企業、スモール・ビジネスの経営の解明が必要なのである。
永続的成長企業ネットワーク 理事
横浜市立大学名誉教授・放送大学客員教授
斎藤毅憲
- 開催日2016年11月5日
- 場所
- 時間
- 費用