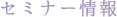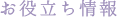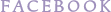【誌上テーマ別サロン】第22回
<基礎講座>
「企業はあまり大きくならない」仮説
―「中小企業経営学入門」(22)
1 例外的な存在としての大企業
・企業の総数からみると、大企業の数はきわめて少なく、例外的な存在といえる。新聞の株式欄をみるとわかるように、株式市場への上場企業は決して少ない数ではなく、かなり多くあるものの、企業総数に対する比率でいうと、きわめて低いのである。
・要するに、例外的といえるが、日本経済を支え、雇用人口の約3割を占めている大企業の数は上場企業でみるとかなりのものに及んでいる。矛盾したいい方になるが、それが正しい表現になるであろう。
・これらの大企業のなかには、企業グループのように、大企業がつくった子会社もあるが、もともとはスモール・ビジネスから出発している。「スモール・ビジネスは成長して大企業になる」とか、「町工場からグローバル企業へ」の仮設については、それを実証する企業は沢山あるといえる。
2 「企業はあまり大きくならない」仮説の妥当性
・しかし、企業総数のほとんどが小さなままである。このことから企業をあまり大きくならない存在として捉えることも妥当ではないかと考える。周辺にある商店街の店舗は長いこと同じ規模であるし、飲食店は同じお店でがんばっている。少し利用者が増えても、店舗を拡大するとか、店舗数を増やすところまでには行かないのである。
3 大きくならない理由
・起業して最初に直面する課題とは、あたり前のことであるが、自社の製品やサービスのユーザー(顧客)の獲得である。売るべき製品やサービスがあっても売ることができなければ企業としての活動を継続することはできない。しかし、この段階を越えていかなければならない。
・つぎの段階では、コストを上まわる売上高を得なければならない。しかも、それをつづけいくことが必要である。それができれば経営は安定軌道にのり、短期の経営計画を作成し、これにもとづいて経営ができるようになる。そして、第3の段階ともいうべき成長の軌道に進むチャンスが生まれる。
・しかし、他の企業の製品によって自社製品が売れなくなり、顧客の獲得ができなくなったり、減少するようになれば、成長の軌道から第2の段階や悪い場合には第1の段階の間を行ったり、来たりすることになる。したがって、株式上場とか大企業化は、スモール・ビジネスにとって大きな飛躍やジャンプを意味している。
永続的成長企業ネットワーク 理事
横浜市立大学名誉教授・放送大学客員教授
斎藤毅憲
[2016.7.5]
- 開催日2016年7月5日
- 場所
- 時間
- 費用