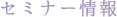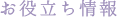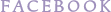【誌上テーマ別サロン】第20回
<基礎講座>
スモール・ビジネスの経営は本当に劣っているのか
―「中小企業経営学入門」(20)
1 「企業イコール大企業」:経営学者のステレオタイプの問題点
・経営学者のもっているステレオタイプ(偏見)のひとつに、企業とは大企業のことであるというのがある。20世紀の初頭にビッグ・ビジネス(大企業)が成立し、これを研究対象にして経営学が成立・誕生したという経緯からいえば、それはステレオタイプではなく、真実である。だが、企業総数からいえば99%以上が中小企業であるという現実に照らしていえば、この等式はまさにステレオタイプといえる。
・しかし、問題は経営学者がスモール・ビジネスにはほとんど関心がなく、その経営について十分に分析したり、説明してこなかったことである。つまり、大企業には役立ってきたかもしれないが、スモール・ビジネスのためには有効な貢献をしてこなかったということである。
2 スモール・ビジネスの経営は劣っているのか
・このような問題のなかで、もっとも疑問になるのが、スモール・ビジネスの経営が大企業のそれに比較して劣っていると考えられてきたのではないかということである。資本も少なく、労働集約型の経営は能率があがらず、生産性が低いのである。これに関連して、人事上の待遇でも大企業にくらべたら低く、雇用も安定していないとみられてきた。
・また、環境変化への適応能力もないと考えられてきた。したがって、どうみても大企業に比較して、スモール・ビジネスの経営は劣っているとみられても仕方がないことであった。
・さらにいえば、小さな企業はその経営によって成長して、大企業になっていく。とすれば、大企業はスモール・ビジネスのすぐれた経営の結果(アウトカム)であるということもできる。もっとも、これには、企業の成長をどう考えるかという問題がある。
3 質的に異なる経営
・しかし、スモール・ビジネスと大企業の経営を比較する場合、大企業のほうがすぐれていると結論づけるべきではないと考えている。確かに、上述の話も納得できるが、両者の経営はむしろ質的に異なるものであり、スモール・ビジネスにはそのための経営があり、大企業には大企業なりの経営のあり方があるのではないか。したがって、どっちがよいのか、すぐれているのか、という議論には組しないことにしたい。小さなマーケットを対象にしているスモール・ビジネスが大量の資金を投入してマス・プロダクションを行う必要はないことは、明らかであろう。
永続的成長企業ネットワーク 理事
横浜市立大学名誉教授・放送大学客員教授
斎藤毅憲
[2016.5.5]
- 開催日2016年5月5日
- 場所
- 時間
- 費用