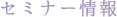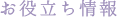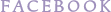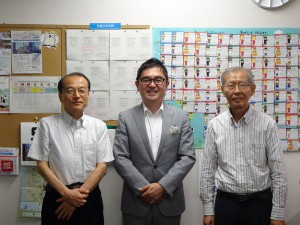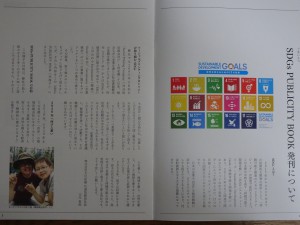【訪問型サロン】(第5回)
<Yokohama Excellent Company (YEC) 第5回>
『㈱大川印刷の大川哲郎社長に聞く』(その3)/3回連載
1 日 時 2018年7月5日
2 場 所 ㈱大川印刷横浜営業所HEAD OFFICE FACTORY
3 聞き手 永続的成長企業ネットワーク代表理事 吉田正博
々 理事 斎藤毅憲(文責)
4 内 容 以下の通り((その2)の続き)
・社長になるための苦労 今回のサロンのなかで興味深かったもうひとつの話は、若くして「孤独な存在」としての社長にならざるをえなかった自分の道のりを述べてくれたことであった。父親や長兄の突然の急死のなかで社長に就任し、現在に至るまでに、いろいろな経験や思いをしてきたという。いろいろな人と出合い、そのなかでの話を教訓にしてきたことも明らかにされた。私と社長のつながりは、おそらく横浜の青年会議所がCSRの研修をはじめた2004年頃からはじまっているが、いつもの明るい笑顔の背後には若いときの苦い思いがある。むしろ、それがあってこそ現在の笑顔があるのだろう。
・教訓の例示 そして、改善・改革を行い、失敗しつつ、学んだ教訓をいくつか教えていただいた。
① あらゆることは自身の選択によって行っている。
② 人を変えることはできないが、自分を変えることはできる。
③ 真に自分が変わると人も変わる。
④ 正しい行ないを見ている人は必ずどこかにいる。
⑤ 救われた一言・・・・「『経営』とは続けることです。」
これらはほとんど人生訓である。やさしい言葉で述べられているが、そのとおりである。CSRを先駆的・先導的に行い、たえず改善・改革してきた経験のなかから引きだされたものであり、とくに①、②、③は至言である。さらに私にとって興味を感じたのは、④である。おそらくCSRを実践する経営を行うなかで、理解を得られず、顧客、取引業者、同業者などのステイクホルダーのなかには離反したり、場合によっては、悪意のある言葉を投げつけられたかもしれないが、他方で社長の行動を正しく評価する人びとも確実に存在していることである。
・新しいことを率先して行うには、勇気が必要である。そして、いいことをいわれないほうが多いかもしれない。しかし、正当に評価し、サポートしてくれる人もいるのも事実である。これは、社会問題を解決しようとし、その際これまでには考えられなかったようなことで事にあたらなければならない経営者には、とくにあてはまる。変えることは大変であり、抵抗もあるが、現代は変えることが常態であり、それは恐れてはならない。そして、それを評価する人びとが確実にいる。④はそれを示している。
・「幸せの創出」というミッション なお、社長の話のなかで気になったのが、経営を行ううえで、幸せの創出が大切であるということである。横浜の印刷業の先駆者として、横浜の印刷の歴史と文化を内外に発信したい思いとならんで、「仕事を通じてひとつでも多くの幸せを創出すること」が、同社のミッション(ビジョンや志)であるという。これまでの訪問型サロンでも、石井造園の石井社長が同じように“幸せ”をつくりだすことを大切にしていると述べたことを思いだした。
企業は“幸せ”をつくるための組織であることを再確認すべきであろう。働く人びとがつらく、大変な思いをしている企業も多い。なんのための企業かということが無視され、売上高や利益を得ることのほうが重視されている現実もある。要するに、企業の目標がなにかを確認できる話を聞くことができた。
・社長の2枚目、3枚目の名刺 サロン終了後、社長から2枚目、3枚目というべき名刺をいただいた。裏面には、B.B.Kingのメッセージのある言葉が書かれていた。
“The Beautiful Thing About Learning is That No One Can Take It Away From You”(学ぶことの素晴らしいところは、誰もあなたからそれを奪うことができないことだ。)
“People All Over The World Have Problems. And As Long As People Have Problems,
The Blues Can Never Die”(世界中の人びとには問題があります。人びとが問題をかかえているかぎり、ブルースは決して死ぬことはできません。)
名刺の裏面に、このようなメッセージのある言葉を載せることはほとんどないであろう。しかし、社長は、Kingの言葉に共感しているから、載せたのだと考えている。
・社長へのアドバイス 吉田代表理事と私からの社長へのアドバイスは、社長の社会的な評価が高まることから派生する問題に対する危惧であった。社会的な評価が高まるにつれて、行政などの外部委員に任命される結果、社長が本業に専念しづらくなるのではないかをわれわれは、心配していたのである。行政などの仕事を通じても、“幸せ”の創出はできるが、社長にはどこまでも本業のビジネスによって“幸せ”をつくってほしいと思っている。
[以上 (その3)/3回連載]
[2018.8.24]
- 開催日2018年7月5日
- 場所
- 時間
- 費用